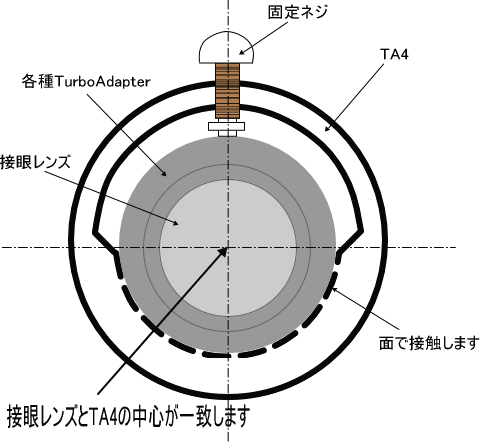« 【やりたいこと】 今朝、ふと思った(笑) | メイン | 【作品募集中】 第10回デジスコ写真展ご案内 »
2013年05月31日
【新製品 予告】 接続カプラー TA4-2
TA4-2.(ティーエーフォー マイナス 二)
接続カプラーTA4よりも約2㎜接眼レンズとカメラレンズを近づけることができるパーツです。
例えば、KOWAのワイドズームアイピース&TurboAdapterP2とTA4シリーズで接続する場合、
レンズ間クリアランスを最短にセットできる接続パーツはTA4でした。
しかし、あとちょっと近づけたい・・・という状況もあるため、そのようなニーズにお応えするための
スペシャルチューニングパーツとなります。
初心者・入門者が使う場合はしっかり技術的な説明を聞いて、鏡筒が衝突しないように設定しなければなりません。
従って、この商品は通常商品とはせず、チューンナップ専用品とするため技術説明を状況に応じた状況でできる販売店のみの取り扱い商品とします。
初回生産は30個。価格は9000円(税込)となります。(TA4シリーズより高額になります)
発売開始は2013年6月下旬。
次回、生産はニーズに応じて、TA4シリーズ生産時に同時製造のため未定です。
以下に『デジスコ用アダプター進化論 (カプラー編)』 を記します。
デジスコの光学的性能を高めるためには光軸をずらさない工夫が重要である。「観察がメインで撮影は記録できればいい」という目的なら気にしなくても良いのかも知れないが、良い写真を撮りたいならば光の入射からデジタルカメラCMOSまではできる限り光軸をずらさないようにすることが画質の向上につながることは間違いない。
一般的なデジスコの場合、フィールドスコープ(スポッティングスコープ)内部の光軸とカメラ内部の光軸は光学機器メーカーの範疇であり、ユーザーが安易に触ることはできない。ユーザーが留意すべき光軸調整はスコープとデジカメの接合部、いわゆるアダプターである。
光学機器メーカーから一般市販されているアダプターの設計は光軸をきっちり配慮してあるかというと・・・正直、「これなら!」といえるものは見つからない。
観察重視でパートタイム撮影形式のアダプターについては、光学性能について今後何かしらの進歩があるかも知れないが、カメラをカメラ底部のカメラネジだけで固定し、上下左右及び入射角を任意な目分量で決めて固定する方式の観察重視&カメラ選択の汎用性を高めた形式のものは光軸を正しく導くことはかなり難しいと理解してほしい。あくまでも「観察&利便性重視」であって「画質重視」とはいえない。
画質を重視するならばつなぐことでスコープとデジカメを機械加工精度レベルで一体化できる形式の接合方法を選ぶのが良い。ここでの解説はこの「カプラー方式」を中心に話を進める。
●第一の進化 TurboAdapter TA3(生産終了)
まずは、ご自分のシステムのチェックをして頂きたい。スコープとカメラを接合し、接合固定ネジをしっかり締めてからスコープとカメラを持って左右上下に応力をかけてガタツキを見て欲しい。しっかり一体化されていないでカタカタ動くようであれば光軸の安定性は望めない。
しかし、このガタツキは必然によるものでもあり一概に「悪い」とは言えない事情もある。凸アダプターにカプラーをかぶせる場合、寸法差を"0"に近づければより光軸や固定精度は向上する。しかし、寸法差を小さくすればするほど着脱性は難しくなる。従ってユーザーが使用できる範囲でクリアランスを作る必然がある。
現状市販品で一番クリアランスが小さいTurboAdapterTA3はTurboAdapter各種(NikonDSシリーズなど)に対し、最小限のクリアランスとしてあるが、一般的なユーザーがストレス無く着脱できる度合いにしてある。特にTurboAdapterは凸アダプターも導入部も入りやすい形状にし、組み合わせて使うことでより効果的である。
カプラーのTA3と同形状のNikon FSA3(またはFSB-1カプラー部)とクリアランスの大きさを比較して欲しい。Nikon FSA3は多くのユーザーに安価に使われることを目的に、機械加工や手作業を最小限にする工夫がなされている。例えば、固定ネジの脱落損失を防ぐために内面に同心円状に溝を切り、外側から台座付きネジを差込、内面の溝にストッパーであるEリングが収納できるようになっている。凸アダプター(FSA1,FSA2、DSシリーズなど)とカプラー(FSA3、FSB1など)は同等の設計思想で着脱性を重視した構造になっている。
クリアランスの小さいTurboAdapterTA3については着脱性が悪いと考えられるが、実際に試してみるとNikon純正品に比べても着脱しやすいことがわかる。これは、固定ネジの脱落防止のために作られた内面の溝の有無が大きく影響している。内面が平滑なTA3はTurboAdapter20XWFA(接眼レンズアダプター)の導入部の曲面と相まって滑るように導入される。これに対し純正接眼レンズ(DS接眼レンズなど)は導入部に曲面が無く角ばっており、また、カプラー内面にひっかかりを起こす溝があるためクリアランスが小さいTA3であっても着脱は容易になるわけである。
接合部の内径・外径の差が大きいことによるデメリットは着脱性だけではなく、光軸保持に大きく影響を起こす。内径に比べ小さな外径を組み合わせた場合、光軸の平行なズレが若干現れるが画質にはあまり大きな影響はない。画質に影響するであろうことは固定ネジを締めた状態で起こる対向面での線接触による上下を支点とした左右のガタツキを要因とした光軸の角度ズレと固定ネジの緩みである。TA3はカプラー肉厚を可能な限り薄くし、固定ネジを締め付けることにより、若干の弾性変形を起こさせ、相応の変形をさせることにより線接触を可能な限り面接触させることにより固定時のガタつきを押さえ込む事に成功した。58mm接続ネジ側は断面二次モーメントが大きいので多少無理のある変形であるが線接触に比べ効果は大きい。しかもカプラーの変形により固定ネジに応力がかかるため緩み防止にも効果がある。
● 第二の進化 新開発 TurboAdapter TA4
前述の解説で光軸を作り、保持することがデジスコを快適に楽しむことに重要であるかが理解してもらえたと思う。スコープ・接眼レンズ・カメラの光学系については自由に調整できないので、着脱要素を持ち、光軸保持を要求されるアダプター部位の工夫や精度が要求される。
例えば摺動性の高い四フッ化エチレン(テフロンなど)を内面にコートして極限までクリアランスを小さくし、表面処理剤の変形に期待して面接触させる手段もあるが、すでに内径・外径のクリアランスは1/100mm台まで精度が高められていて、さらに膜厚コントロールがし難い有機系弾性表面処理は技術的に困難である。また、カプラー自体をテフロンなどから切削しても金属とプラスチックの伸縮性(10倍)の差からコントロールができない。
内径と外径が同じになればすべて面接触するため光軸のズレなどの心配は無い。しかし、いわゆる勘合状態であり、着脱は不可能である。という常識を乗り越え、面接触と着脱性を追及して考案し、新規に製品化されたものがTurboAdapterTA4である。
高精度な金属加工機を駆使し、カプラー内面の半円弱の部分をアダプターと同径とし、固定ネジ側の半円強を着脱用のクリアランス部分としたものである。固定ネジを締め付けることにより対向する半円がアダプターと面接触し、固定ネジ側の締め付け力と弾性変形の応力で面接触を確実なものにできるので、理屈では接合時の光軸の角度ズレや平行ズレも無いことになる。さらに、固定ネジ材質をアダプター表面処理(アルマイト)より硬度が少ない材質にすることによりアダプターへの傷を回避する工夫などもされている。
加工手段に手がかかり高価になるが、実際に使用するとTA3との差もしっかり感じる。このフィット感は他の手法では得られないものと思える。より、高い接合要件を満足させたいユーザー向けのアイテムである。
同様の効果を従来のカプラーで体感することもできる。例えばNikon純正のアダプターの固定ネジに対向する半円弱部分に厚さ0.1mm程度の薄いテープなどを貼ることでもガタツキを若干抑えることはできるが、着脱性や耐久性では物足りないかも知れない。TA3の場合は0.03~0.04mm程度のテープが良いが、着脱性ではかなり苦労する可能性がある。
投稿者 たーぼ♪ : 2013年05月31日 23:05